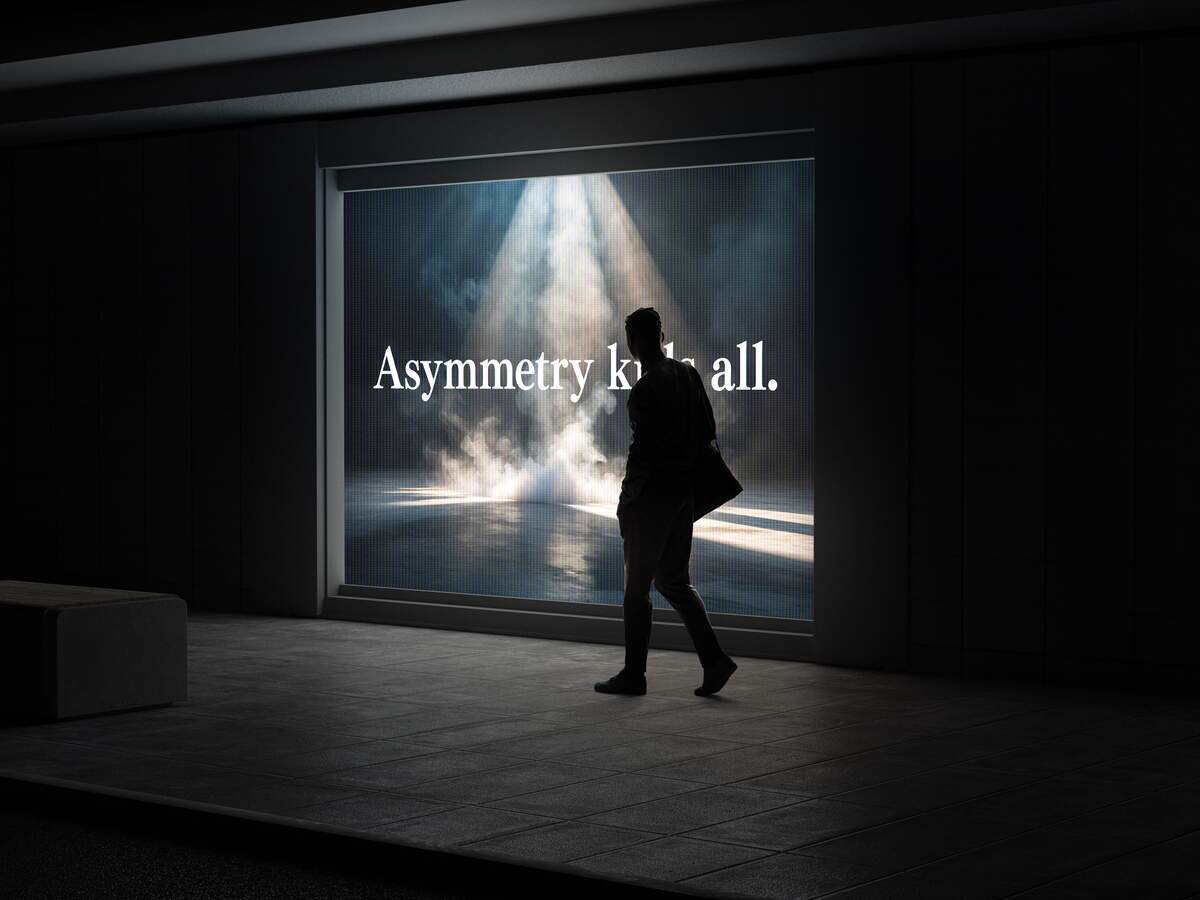 今日も今日とてYoutubeは大賑わいだ。ここ数日、映画系Youtuberのトレンドはもっぱら『白雪姫』で、猫も杓子も異口同音に「酷評」を陳情している。
今日も今日とてYoutubeは大賑わいだ。ここ数日、映画系Youtuberのトレンドはもっぱら『白雪姫』で、猫も杓子も異口同音に「酷評」を陳情している。
どうして公開前から地雷だと分かっている作品を観て、わざわざ酷評するのか、『室井慎次』が公開された頃にはさっぱり分からなかったのだけれど、最近ようやく「酷評」すれば再生数が稼げるらしい…という実態を知った。
僕もYoutubeをやっている同じ穴のムジナなのだが、近頃とみにYoutubeが息苦しい場所に感じられてならない。元来、ブログで「テキスト」を用いて書いていた映画の感想を動画としてパッケージングするだけで不特定多数の視聴者が反応してくれる。中身(コンテンツ)は同じなのに、装い(パッケージ)を変えるだけで反応が桁違いに増進する。なんとも不思議な世界だなと、チャンネルを開設した当初はそう思っていた。
そしてチャンネル開設から1年余を経た今、Youtube界隈の実情がだんだんと分かってきた。Youtuberの至上命題は1つしかない──チャンネル登録者数や再生数といった数値をどれだけ高くできるか。全てが数値に還元されるプラットフォームで、いかにハイスコアを狙えるか。再生数や登録者数、あるいは収益。これらの数値をいかに効率よく、確実に獲得できるか。まるでゲームだ。
予告編の段階からすでに面白くないと分かりきっている地雷映画をわざわざ高い木戸銭を払ってまで観に行って酷評するのは、それが最も効率的にハイスコアを狙える戦術だからだ。2000円の木戸銭ぐらい、1つの動画の収益でリクープできるから問題ない。おそらくそういうことだろう。
ことほどさように、Youtubeを取り巻く状況は、玉石混交の企業が繰り広げる資本主義のゲーム──利益至上主義のビジネスと相似形を帯び始める。余暇の時間を使って趣味として動画を投稿しているのに、その余暇の時空間にも仕事の影がちらついて見える。これがなんとも息苦しい。
この息苦しさを解消する方策を今年に入ってから色々と模索していたのだけれど、最近、諦めた。
長いものには巻かれろ。押してダメなら引いてみろ。Youtube=プラットフォームとその経済スキームを変えられない以上、Youtubeという土俵に上がった僕はそれに唯々諾々と従うよりほかにない。いくら体制に異を唱えても何も変わらないし、変えようがない。だから僕は、ジョージ・オーウェルの小説『1984』のごとく、二重思考《ダブルシンク》を決めこむことにした。体制に従いながら、体制に対して心の奥底では中指をおっ立てる。ザ・クラッシュのジョー・ストラマーが言ったように、「punk is attitude not style」である。デジタル・レーニン主義をサバイブする処世術。それは二重思考だと思う。
そんなふうに、Youtubeをクソ喰らえと思いながらも、いまだ性懲りもなく動画を投稿し続けているのは、常連さんとのコミュニケーションが楽しいからだ。類は友を呼ぶという慣用句が本当なのか分からないけれど、僕のチャンネルにいつもコメントをくれる常連さんが居る。毎回動画を投稿するたびにコメントを書き込んでくれて、僕はそのコメントに時に共感し、時に唸らされながら、返信を投稿する。
XやLINEのような即時的な会話ではなく、動画を投稿する1週間というスローペースで進行するコメントの往復。この掲示板じみた速度感が好きだし、自分と似たような感性の持ち主たちと「面白かった」という感想を共有するのが好きだ。
Youtubeというプラットフォームは心底嫌いだが、それでも土俵から降りたくないのは、ひとえにこの常連さんとの会話が楽しいからという理由に尽きる。
僕がささやかな楽しみにしている常連さん達とのコメントの応酬は双方向的(インタラクティブ)なコミュニケーションだが、悲しいかなYoutubeに付随するコミュニケーションの多くは非対称的だ。そしてこの一方向的・非対称的なコミュニケーションこそが、Youtubeを息苦しい場所に仕立てている。
非対称性
公開翌日、『ウィキッド ふたりの魔女』を観た。オズの国では動物たちが不当な扱いを受けていて、それを象徴づけるセットピースとして檻に入れられたライオンが登場する。この場面を観た時、僕の頭に浮かんだのは現下のSNSを取り巻く諸相だった。檻に入れられたライオンは、檻の外から人間に棒で叩かれて恐懼している。逃げ場もなく、なすすべもなく、ただ振るわれる暴力に忍苦するほかない状況。
昨今のSNS空間はこの檻と同じ構造を有している。Xでなにかを投稿した瞬間、投稿主は檻の中のライオンと同じ状況に陥る。どこで誰が見ているかも分からず、引用RPされるならまだしも、スクリーンショットを撮られて自分のあずかり知らぬところで拡散されるリスクがある。Youtubeに動画を投稿すれば、不特定多数の視聴者が動画を視聴し、動画にコメントを投稿する。投稿者はそのコメントを受け取ることしかできず、公開設定でコメントをシャットアウトしてしまえば再生数が目減りしてしまう。
とりわけYoutubeの映画界隈では動画投稿主/視聴者の他にも、映画作品/動画投稿主の間にも映画作品/観客の間にも、コミュニケーションの非対称性が成立している点が皮肉だ。映画の作り手たちは心血を注いで作品を世に送り出し、そのあとは観客たちの裁きを待つほかない。一度、映画館にかかった映画を公開後に回収することは能わず、一度作品が世に送り出されると、作り手たちは観客の評価を受け入れるしかない。そして、映画を観た感想を傍若無人に語るYoutuberもまた、この非対称性に甘んじて好き好きに感想を語り、それを動画としてコンテンツ化する。ここでもYoutuberと映画製作者の非対称性が成立している。そして、そんな動画投稿主たちもまた、不特定多数の視聴者から寄せられるコメントによって、非対称的なコミュニケーションを押し付けられる。まるで負の連鎖だ。一方通行のコミュニケーションが連鎖し、視聴者の感情が再生数によって数値化されて可視化され、彼らの感情が増幅されて、それが新たなコメントを生み出す…
この非対称性のチェーン・リアクションが行き着く最果てこそ、「酷評」動画だ。
褒める技術
作品を世に送り出し、観客の裁きを甘んじて受け入れるほかない映画製作者。彼らが心血を注いだ作品を再生数を稼ぐため、Youtubeというゲームでハイスコアを叩き出す目的で無責任に酷評するYoutuber。その動画に大挙して押し寄せる視聴者。酷評に便乗する彼らのコメント。すべてが非対称性で占められている。
デジタル上におけるカンガルー裁判。これがYoutubeで日々生成され、もっとも視聴数を稼げるコンテンツの正体だ。そして、この状況をより複雑にしているのは、映画という娯楽の持つ性質──互いに感想を言い合うファンコミュニティに寄生する映画の性質だ。
観る人の数だけ違った感想があって当然だし、その差異を互いに交換しあうことに映画の感想を語る愉しみがある。だから酷評するのも自由なのだ。本来は。だがYoutubeで酷評すれば、マネーゲームと非対称性に絡め取られてしまう。だからYoutubeで酷評する行為は悪辣なのだ。
映画を観て文句を言うのは容易い。「なんでもかんでもフェミ化しやがって…クソだ」感情にまかせて、不特定多数がもっとも共感するであろう最大効果域を狙って火種を放り込めばいいのだから。
Youtubeで映画を語るのは批評とはまったくの別物、どこの馬の骨とも分からぬ一般人の感想に過ぎない。だから厳密には酷評という言葉を冠する資格はなく、単なる「文句」に過ぎないのだけれど…はたして、映画を酷評した動画が人気コンテンツとして横溢するYoutubeの現況が、正常と言えるのだろうか。
批評家の小林秀雄は『考えるヒント』の中で、批評とは何かを次のように記している。
批評とは人を褒める特殊な技術だ、と言えそうだ。
不特定多数の無知と激情が暴走した結果、ソクラテスは殺された。ソクラテスの生きた紀元前5世紀半ばのアテネは、古代民主制を確立し、豊かな文化を有していた。だが同世紀後半になると戦争に巻き込まれ、混乱と衰退が始まる。ソクラテスの裁判はそんな状況下で執り行われた。ソクラテスは独裁者によるカンガルー裁判で処刑されたのではない。彼を不当に非難し、死に追いやったのは無知な市民であり、刑を宣告したのも市民だった。偉大な知は、低俗なポピュリズムによって殺された。
歴史家は言う。歴史は繰り返す。それは人が歴史から何も学ばないからだ。何も考えないからだ。舞台が現実世界からデジタル空間に遷移しただけで、事態は紀元前から何も変わっちゃいない。
今やNetflixに代表されるメディア・コングロマリットが支配するエンターテイメント業界、とりわけ映画産業。
ラテン語の「役に立たない(enter)」と「tenue(楽しい)」を組み合わせた複合語=エンターテイメント。
べつに無くても生存には困らない。けれど、楽しいもの。それが娯楽であり、映画であったはずだ。
映画を不当に貶め、その状況を『BREAKING DOWN』を観るのにも似たピーピングトム的な視点で享受するYoutube映画界隈の現況は、娯楽の「愉しみ方」を履き違えている。
では、映画とは何なのか? 一生かかっても答えが出ない(出るはずもない)深遠な問いに、偉大な映画評論家は有効な補助線を提示している。
映画は映画論文のためのものではありません。映画は心にしみこむ芸術であって、いうならば人間形成の最ももっとも重要なものを生きた目に見せ、生きた心にしみこませ、ゆたかな人間を生んでゆく、生きた教科書だと信じています。
淀川長治 『淀川長治 映画塾』